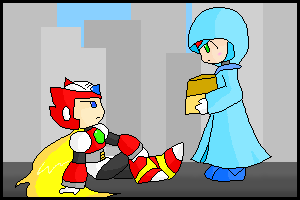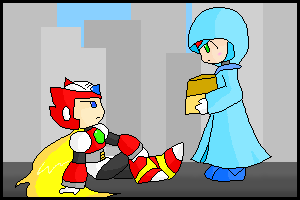
「救難信号を出していたのは、あなたですか。」
|
起動してから1週間のエックスにとって、たった一人で「お留守番」をするのは初めての事だった。 ライト博士が急な用事で呼び出され、ロックはそのお手伝いについていった。 エックスの兄にあたる他のライトナンバーズ達は、みんな仕事に出ているし、 いつもは家にいるロールもお買い物に出かけている。 エックスはきれいに片付けられた部屋の隅っこにしゃがみこんだ。 退屈だ。何もすることがない。 どうしてだろう、とエックスは考えた。彼の兄達は、それぞれの特性に合わせた仕事に就いているのに。 自分に兄達を上回る性能が与えられている事を、エックスは知っている。 それなのに今のところ彼には何の役割も与えられていない。宝の持ち腐れだ。 自分が何のために作られたロボットなのかよくわからない事が不安だった。 考えているうちに、気分が沈んでしまった。 研究室でデータベースでも見ていようと思って、エックスは立ち上がった。 ライト博士はこんなことを言っていた。 お前は自分で考え行動する新しいタイプのロボットになるんだよ 今はいろいろな事を学んで、その心を育てる時なのだ、と。 研究室のコンピュータを起動しようとした時、見覚えのあるツールボックスが床に落ちているのに気が付いた。 昨日、エックスの兄の一人であるエレキマンに見せてもらったものだ。 彼は発電所で働いていて、機器の調整や修理をする事もあるらしい。 これには、仕事で使う道具が入っているはずだ。 どうしよう、忘れ物かな。エレキマン、困っているだろうな。 届けに行くべきだろうか、とエックスは少し悩んだ。 ライト博士に、外には出ないようにと言いつけられているのだ。 お前は新しいタイプのロボットで、世間に出すにはまだ早い、と。 それでも、困っているであろう兄を放っておくことはできないと思った。 新型のロボットだって、ばれなければ大丈夫かもしれない。 そんな事を思いついて、エックスは衣装棚の中から大きめのレインコートを引っ張り出してきた。 フードを深めに被って、自分の姿を鏡で確認してみる。 青いアーマーの殆どは隠れているし、エックスの体格は人間とそう変わらない。 ちょっとすれ違った位では、ロボットだと気付かれないだろう。 荷物だけ渡して、すぐに帰ってくればいいのだ。 ツールボックスを抱えて、エックスは初めて外に出た。 ----------------------------------------------------------------------------------- 悪の天才科学者・DRワイリーの最高傑作であるゼロは、機嫌が悪かった。 動けないし、脚は痛いし、自動で発せられる救難信号はうるさい。最悪な気分だ。 どうしてこんな事態になったのかを思い返す。実にくだらない話だった。 つい数十分前まで、ゼロは、ワイリーに脚部パーツの調整を受けていた。 そこにフォルテが帰ってきて、ワイリーと口げんかを始めてしまった。 ワイリーとフォルテの言い争いなどいつもの事で、しばらく放っておけばいい事をゼロは知っていた。 しかしゼロはワイリーの作業が終わるまでは動けない。 彼は大人しく待っているということがあまり好きではなかった。 退屈で、少々イライラしていたのかもしれない。なので、つい2人の言い争いに口出ししてしまった。 …そして、ゼロと、彼の兄と製作者は、いずれも負けず嫌いで意地っ張りだった。 3人で盛大に口げんかを繰り広げた挙句、ゼロは作業の途中だったのにも構わず研究所を飛び出してしまった。 腹いせに暴れまわってやる、などと考えながらビルの上を飛び移っていたら、脚部パーツを損傷して 落下してしまい、今に至るというわけだ。 そのうち救難信号をキャッチして、ワイリーか、ワイリーナンバーズのロボットが迎えに来るだろう。 嫌味の一つや二つを言われるのは免れないだろうと思うと余計に気分が悪くなって、 耳障りな音で鳴り響く信号を強制的に切った。どうせ居場所はもうわかっているだろう。 ゼロの落下した地点は狭いビルとビルの隙間で、人通りは無いのが好都合だった。 誰かに見つかったら、面倒なことになるだろう。 いくらか経ってから、ゼロは誰かの足音が近づいてくるのに気付いた。 …人間の足音ではない。ゼロの兄―ワイリーナンバーズ達とも違う。 面倒なことになるかもしれない、と身構えた。 ゼロの前に現れたのは、奇妙な格好をしたロボットだった。 彼より少し小柄な人型で、両腕に大きなツールボックスを抱えている。 そして、何故か晴れているのにレインコートを着込んでいる。 未知のロボットは、ゼロに対して警戒する様子も無く話しかけてきた。 「救難信号を出していたのは、あなたですか。」 ゼロは相手の様子を用心深く伺いながら、そのロボットの個体識別信号を読み取った。 『DRN-XXX ”X”』 DRNが何を意味するか、ゼロは知っていた。敵だ。 ワイリーの野望をことごとく阻止し、長年に渡ってワイリーナンバーズと戦いを繰り広げている ”ロックマン”と、その兄弟機の総称であると、ワイリー研究所のデータベースで見たことがある。 しかし、目の前にいるロボットのデータは記載されていなかった。 最近開発された新型機かもしれない。警戒を強めるゼロとは逆に、 小さいほうのロボットは穏やかな様子だ。こちらの正体には気付いていないのだろうか。 「あの、わたし、簡単な修理ぐらいならできます。道具もありますし…。」 下手に警戒した様子を見せたら、怪しまれるかもしれない。 「脚、見せてもらえますか?」 ”X”から敵意は感じられない。素直に相手の助けを受けた方が良さそうだと判断し、ゼロは頷いた。 幼い顔つきと、どこか頼りなげな口調とは裏腹に、エックスは意外と器用に修理を進めている。 「そんなに損傷は酷くないみたいです。ここと、ここのパーツが外れてましたよ。」 …こいつをどうするべきだろう。本来ならば破壊してワイリーに報告すべきなのだ。 しかし、何故かゼロはそうする気が起きなかった。 この無防備で、親切なロボットに危害を加えるのは気が引ける。 ワイリーの野望のためだけに造られた、純戦闘型のロボットがそんな事を考えるなどありえないはずで、 ゼロは戸惑った。 「終わりましたよ。応急処置ですから、後でちゃんとした所で直してもらってくださいね。」 そう言って、立ち去ろうとするエックスに、ゼロは話しかけようとした。 「おい、」 しかし何を言えばいいのかわからない。沈黙を破ったのは、エックスの方だった。 「もう行かないと…。それじゃ、お大事に…お姉ちゃん。」 おいこら待ちやがれ誰がお姉ちゃんだこのやろう。 とゼロが言い返す前に、晴れているのにレインコートを着た変なロボットは走り去ってしまった。 先ほどまで考えていた感情の変化もどうでもいいような気分になって、 とりあえず次に会ったら一発ぶん殴ってやろうとゼロは誓ったのだった。 |